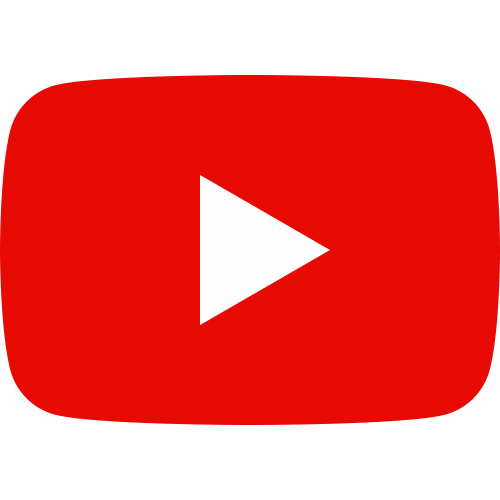目次
「どうして自分の歯並びはこんなにガタガタなんだろう?」「子どもの歯並びが悪くなってきた気がするけど、原因は何?」と思う方もいるでしょう。歯並びの乱れに関してさまざまな疑問を持つ方は少なくありません。
この記事では、歯並びが悪くなる原因から、放置することによるリスク、そして歯並びを美しく整えるための矯正方法まで詳しく解説します。この記事を参考に、ご自身やお子さまの歯並びについて考えてみてください。
歯並びが悪くなる原因

歯並びが悪くなる原因は一つだけではなく、様々な要素が複雑に絡み合い生じることがあります。ここでは、その主な原因について詳しく見ていきましょう。
遺伝的な要因
両親や祖父母などに歯並びの悪い方がいる場合、同様に歯並びが悪くなる可能性が高くなります。顎の骨の大きさや形、歯の大きさや数などが遺伝することがあるためです。
例えば、顎の骨が小さいのに歯が大きい場合、歯が並ぶスペースが足りずに叢生(そうせい)になることがあります。また、出っ歯や、受け口なども遺伝的な要因が関与することがあります。
口腔習癖や習慣
幼い頃からの指しゃぶり、爪を噛む、唇を噛む、舌で歯を押すといった癖が、顎の成長や歯の並びに悪影響を与えることがあります。これらの癖を長期間にわたって行うと、上の前歯が前方に傾き、下の前歯が奥に傾く出っ歯の原因となることがあります。
また、頬杖をつく、片側だけで噛むといった習慣は、成長中の顎に左右差を生じさせ、歯列に歪みをもたらします。さらに、鼻炎などによって常に口呼吸をしていると、唇や頬の筋肉の発達が阻害され、結果として歯並びが悪くなる要因となることがあります。
これらの癖は、無意識のうちに行われていることが多いため、早期に気づき、改善していきましょう。
顎の成長不足
現代人は、昔に比べて硬いものを噛む機会が減少したと言われています。十分な咀嚼を伴わない食事が、顎の骨の発達を妨げて永久歯が生えるスペースが不足することがあります。
歯が並ぶためのスペースが十分になければ、歯並びが乱れる可能性があります。
歯の生える順番や時期の異常
乳歯から永久歯への生え変わりは、通常、一定の順番と時期に従って進行します。
しかし、何らかの理由でこの順番や時期が乱れると、歯並びに影響を与えることがあります。例えば、乳歯が予想より早く抜けた場合、周囲の歯がその空いたスペースに移動し、後に生えてくる永久歯のためのスペースが不足する状況になることがあります。
また、生まれつき通常の歯の数以上に生えてくる過剰歯や、特定の歯が欠けている先天性欠如歯があると、歯列全体に悪影響を与えることがあります。
その他の要因
上記以外にも、虫歯や歯周病によって歯が失われ対処されていない場合、そのスペースに周りの歯が移動し、歯並びが悪くなることがあります。また、外傷によって顎の骨や歯に衝撃を受けた場合も、歯並びに影響が出ることがあります。
歯並びが悪い状態を放置するリスク

歯並びが悪い状態を放置すると、様々な悪影響を及ぼす可能性があります。ここでは、放置することで起こりうるリスクについて詳しく解説します。
虫歯や歯周病のリスクが高まる
歯並びが悪いと、歯ブラシの毛先が届きにくい場所が増えてセルフケアが難しくなります。これにより磨き残しが増えると、虫歯や歯周病の原因となる細菌の塊(プラーク)が蓄積しやすくなり、発症リスクが高まります。
咀嚼機能が低下する
歯並びが悪いと、上下の歯が適切に噛み合わず、食べ物を十分に噛むことができなくなります。咀嚼が不十分なままに送り込まれた食べ物は、胃や腸などの消化器官に負担をかけ、消化不良を引き起こす可能性があります。
また、十分に噛むことで得られる満腹感が得られにくくなり、過食につながる可能性も指摘されています。さらに、特定の歯にばかり負担がかかったり、顎関節に負担をかけ顎関節症のリスクを高めたりすることもあります。
発音へ影響する
歯並びや噛み合わせは、発音に大きな影響を与えます。特にサ行、タ行などの音は、舌と歯の細やかな位置関係によって発音されますが、歯並びが乱れるとこれらを発音する際に空気が漏れ、発音が不明瞭になることがあります。
これにより、ビジネスシーンや日常のコミュニケーションにおいて発音の問題が生じる可能性も考えられます。
審美性が低下する
歯並びは、顔全体の印象を大きく左右する重要な要素です。不揃いの歯並びや前に突出した歯などは、笑顔の美しさを損なうことがあります。このような審美的な問題は、心理的な側面にも影響を与える恐れがあるでしょう。
自信を失ったり、人前で話すことや笑うことに対して、抵抗感を抱く可能性も否定できません。
全身の健康へ影響する
噛み合わせの悪さは、首や肩の筋肉を緊張させることがあります。頭痛や肩こりを引き起こしたり、全身のバランスにまで影響を及ぼしたりする場合があります。
また、不適切な噛み合わせが原因で体の重心がずれ、姿勢が悪化することも考えられます。
歯並びを矯正する方法

歯並びを矯正する方法にはいくつかの選択肢があり、どの矯正方法が合っているのかは、歯並びの状態、骨格、ライフスタイルによって異なります。それぞれの治療法を以下で詳しく解説します。
ワイヤー矯正
ワイヤー矯正は、金属製のブラケットと呼ばれる部品を歯に接着し、そこにワイヤーを通して歯を徐々に動かす従来の矯正方法です。長い歴史があり、多くの症例に対応できる点がメリットです。
以前は装置が目立ちやすい点がデメリットでしたが、最近では審美性を考慮した白色や透明の目立ちにくい素材も選択できるようになりました。
また、治療できる歯科医院は限られるものの、歯の裏側に装置を装着する舌側矯正もあります。ほとんど装置が見えないため、見た目を気にせず治療が可能です。
マウスピース矯正
マウスピース矯正は、個別に作成された透明なプラスチック製マウスピースを一定期間ごとに交換しながら歯並びを整える方法です。ワイヤー矯正に比べて目立ちにくく、取り外しが可能なため、食事や歯磨きの際の不便さが少ない点が大きな特徴です。
ただし、すべての症例に対応できるわけではありません。複雑な歯の移動が必要な症例や、重度の不正咬合の場合はワイヤー矯正のほうがスムーズに治療が進むかもしれません。
その他の矯正方法
上記以外にも、顎の骨格に大きな問題がある場合に行われる外科的矯正や、子供の成長を利用して顎の骨のバランスを整える矯正治療があります。子供向けの矯正は、将来の正しい永久歯の生え方と顎の成長を促すことを目的に行われます。
歯並びが悪くなるのを防ぐには

歯並びが悪くなるのを防ぐためには、日々の生活習慣を見直すことが大切です。
口腔習癖を改善する
歯並びを乱す大きな原因となる口腔習癖を見つけた際には、早期に意識して改善する努力をしましょう。特に、お子様の場合、保護者の理解とサポートが不可欠です。無理にやめさせるのではなく、優しく説明しながら、改善に向けて取り組めるよう促してください。
必要であれば、歯科医師や専門家に相談することも効果的です。
正しい姿勢を保つ
普段の生活の中で姿勢を正しく保つことは、顎の成長や歯並びに良い影響を与えます。
猫背や悪い姿勢は顎の位置や噛み合わせを不安定にし、歯並びが乱れる原因になることがあります。座る際や立つ際には、背筋を伸ばし正しい姿勢を意識しましょう。
また、睡眠時の姿勢も重要です。うつ伏せ寝や片側だけを向いた横向き寝は、顎に不均衡な圧力をかけるため、歯並びに悪影響を与える可能性があります。できるだけ仰向けで寝ることを心がけ、枕の高さを適切に調整しましょう。
正しい咀嚼を心がける
硬い食べ物をしっかり噛むことは、顎の骨の発達を促し、歯並びを整えるうえで重要です。柔らかいものばかりを好むのではなく、繊維質の多い野菜や硬めの食材をバランスよく取り入れ、食事の際にはよく噛む習慣をつけましょう。
また、片側だけで噛む癖は顎の不均衡な発達を引き起こし、歯並びに影響を与えることがあります。左右の歯をバランスよく使うことを意識して食べましょう。
定期的に歯科検診を受ける
お口の健康を守るためには、定期的に歯科検診を受けることが重要です。検診では、虫歯や歯周病の早期発見・治療ができるだけでなく、歯並びの異常を早期に見つけ、適切なアドバイスをもらうことができます。
特に、子どもの成長期には、歯並びが大きく変化するため、定期的に検診を受けることで早期対応が可能になります。
まとめ

歯並びが悪くなる原因は、遺伝的なものから生活習慣までさまざまです。また、歯並びの乱れを放置すると、虫歯や歯周病、全身の健康、さらには見た目や精神的な健康にも影響を及ぼします。
歯並びの悩みを解決するには、矯正治療を含む適切な対応が必要です。気になる場合は早めに歯科医院を受診し、相談してみましょう。
品川港南歯科・矯正歯科クリニックでは、痛みや施術時間を抑えながら自然な仕上がりの治療を目指しています。マウスピース矯正やセラミック治療、虫歯治療、ホワイトニングなどにも力を入れています。