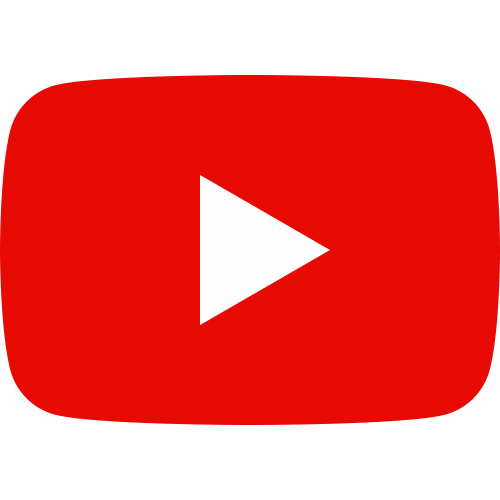「最近、口臭が気になる」「歯周病が原因かな」とお悩みの方もいるかもしれません。歯周病は歯を支える歯茎や骨に炎症を引き起こす病気ですが、実は口臭を発生させる大きな原因の一つです。
特に、歯周病が進行すると強い臭いが発生するため、自分では気づかない間に周囲に不快感を与えている可能性もあります。
この記事では、歯周病による口臭の原因やセルフチェックの方法、効果的な対策について詳しく解説します。歯周病の口臭に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
歯周病で口臭はするの?
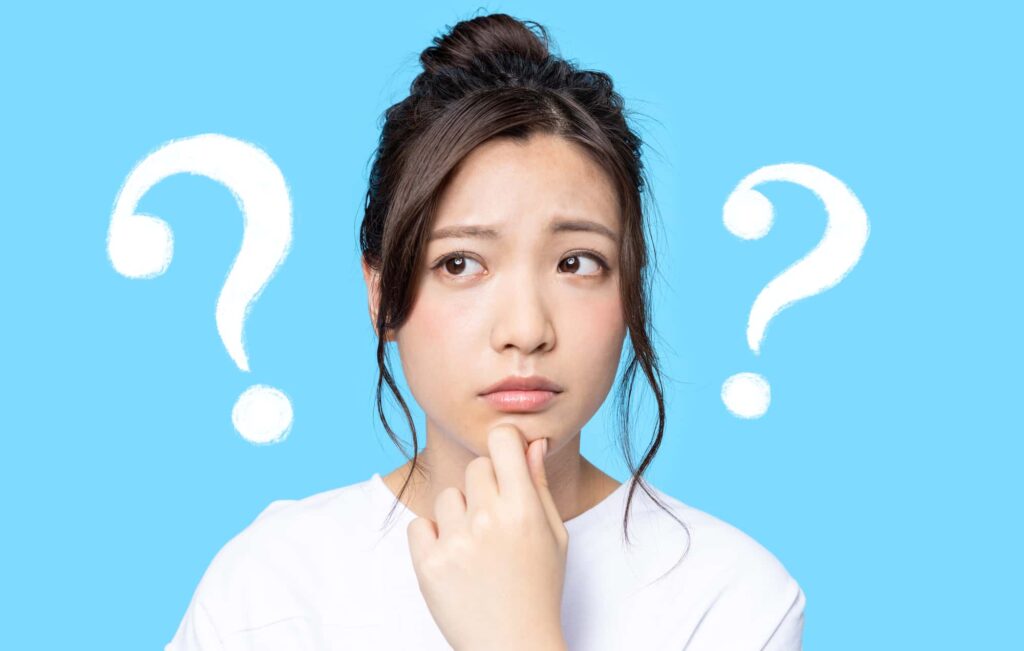
歯周病は、口臭を発生させる大きな原因の一つです。歯周病が進行すると、歯周ポケットと呼ばれる歯と歯茎の間の溝が深くなり、そこに汚れが溜まりやすくなります。歯周ポケット内で細菌が繁殖し、歯周病菌がガスを産生すると、嫌な臭いが発生するのです。
歯周病による口臭はどんな臭い?
歯周病による口臭には、独特の臭いがあります。
歯周病による口臭は、歯周病菌が産生するメチルメルカプタンや硫化水素、ジメチルサルファイドといったガスが原因です。これらのガスは揮発性硫黄化合物(VSC)と呼ばれ、強い悪臭を放ちます。
身近もので例えると、硫化水素は腐った卵のような臭い、メチルメルカプタンは腐った玉ねぎのような臭い、ジメチルサルファイドは生ごみや生臭いような臭いと言われます。その他にも、炎症によって歯茎から出血することで、鉄のような臭いがすることもあります。
歯周病の進行度と臭いの強さ
歯周病による口臭は、歯周病の進行度によって臭いの強さが変わります。
初期の歯周病
歯周病の初期段階である歯肉炎では、歯茎が赤く腫れて炎症を起こし、歯磨きなど少しの刺激で出血しやすくなります。歯肉炎の段階では口臭はほとんど感じられませんが、歯茎の炎症が進行すると軽い口臭が生じることがあります。
中等度の歯周病
中等度の歯周病では、歯茎の腫れや出血に加えて、歯と歯茎の境目にある歯肉溝が深くなり、歯周ポケットが形成されます。歯周ポケットの中に細菌が溜まり、揮発性硫黄化合物が生成されるため、腐った卵や生ゴミのような臭いが発生します。
重度の歯周病
重度の歯周病になると、歯茎の腫れや出血に加え、膿が出たり、歯を支える骨が溶かされたりすることで歯が動揺します。最終的には、骨が歯を支えきれなくなり抜け落ちたり、抜歯が必要になったりして歯を喪失することがあります。
歯周ポケットが深くなり細菌の活動が活発になるため、腐った玉ねぎや卵のような強い臭いを発します。この段階になると、周囲の人に気づかれている可能性が高いでしょう。
歯周病で口臭がする原因

歯周病による口臭は、様々な要因が複雑に絡み合うことで発生します。
歯周病菌が発生させるガス
歯周病は、不十分なセルフケアで磨き残されたプラークが原因で発生します。プラークの中には、歯周病菌をはじめとしたお口の中の様々な細菌が含まれており、プラーク中の歯周病菌が出す毒素で炎症を引き起こします。
歯周病菌は空気が苦手な嫌気性菌のため、酸素の少ない歯周ポケットに入り込み繁殖していきます。これらの細菌は、食べ物のカスや口腔内の剥がれた細胞を分解し、揮発性硫黄化合物を生成します。これが口臭の主な原因となります。
また、歯周病が進行すると歯周ポケットが深くなるため、歯ブラシや歯間ブラシが届きにくくなります。さらに歯周病菌が増殖してガスの産生量も増加し、口臭が悪化していくのです。
歯茎の炎症
歯茎の腫れや出血は、炎症が進行しているサインであり、口臭も悪化している可能性を示唆しています。特に、重度の歯周病では触れただけでも簡単に出血しやすく膿が出ることもあり、この膿も口臭の原因となります。
また、炎症によって歯茎の毛細血管が破壊されると、血液中のタンパク質が歯周ポケット内に漏れ出し、歯周病菌の栄養源となってさらに口臭が悪化します。
唾液の減少
唾液は口腔内の洗浄作用を持ち、細菌の繁殖を抑える役割を果たしています。そのため、唾液が減少すると細菌が増殖しやすくなり、口臭が発生しやすくなります。
舌苔の蓄積
舌の表面に付着する白いコケのようなものが舌苔(ぜったい)です。これには細菌や食べかすが含まれており、口臭の原因になります。
口臭のセルフチェック法

自分の口臭は、以下の方法でチェックできます。
ただし、あくまでもセルフチェックの方法なので、実際に口臭があるか断定できるわけではありません。気になる場合は、歯科医師に相談してみましょう。
コップのにおいをかぐ
コップの中に息を吐いてから一度蓋をし、深呼吸をした後にコップの中の息のにおいを嗅いでみます。少しでもにおいがすれば、口臭がある可能性があります。においのないビニール袋でも代用できます。
舌を確認する
健康な人の舌はピンク色です。舌に白い苔のような物が付いていないか確認し、付いていた場合は、コットンパフなどで拭き取り、そのにおいを嗅いでみましょう。
自分でにおいが強いと感じた場合は、口臭がある可能性があります。
デンタルフロスのにおいをかぐ
歯間の清掃をしたデンタルフロスのにおいを嗅いでみましょう。フロスが臭いと感じるなら、口臭がある可能性があります。
唾液のにおいをかぐ
唾液のにおいでも、口臭をチェックできます。手の甲に唾液を少量つけて乾かし、その後その部分を嗅いでみます。唾液のにおいが臭いと感じたら、口臭がある可能性があります。
歯周病の口臭対策

ここでは、歯周病による口臭の予防法と治し方について詳しく説明します。
歯周病の口臭を予防する方法
まずは、歯周病による口臭を予防する方法を見ていきましょう。
毎日の歯磨きを丁寧に行う
口臭予防には、正しい歯磨き方法で食後や就寝前に丁寧に歯を磨くことが重要です。特に、歯と歯茎の境目を意識して磨き、歯ブラシでは届きにくい歯間の汚れは、デンタルフロスや歯間ブラシを使って清掃しましょう。
舌苔がついている場合は、舌専用のブラシやクリーナーを使用すると良いでしょう。これにより、歯周病菌の増殖を防げます。
定期的に歯科検診とクリーニングを受ける
歯科医院での定期検診とプロフェッショナルクリーニングを受けることで、歯周病の早期発見と予防が可能です。
生活習慣を見直す
喫煙は歯周病のリスクを高めるため、禁煙を心がけましょう。また、ビタミンCやビタミンEを多く含む食事を摂取することで、歯茎の健康を維持できます。
さらに、唾液の分泌を促進し、口腔内を清潔に保つために水分を十分に摂るなど生活習慣を見直すことは、歯周病の予防に役立ちます。
歯周病の口臭の治し方
次に、歯周病が原因で生じた口臭の治し方について見ていきましょう。
歯周病の治療を受ける
歯周病は、歯科医院での専門的な治療が必要です。歯科医院では、歯周ポケット内の清掃や歯周外科治療などが行われます。
歯磨き粉や洗口液を変更する
歯周病の口臭を改善するうえで、毎日のセルフケアは欠かせません。その際、クロルヘキシジンやトリクロサンなどの抗菌成分を含む歯磨き粉や洗口液を使用することで、歯周病菌の増殖を抑制できます。
生活習慣の改善
歯周病の治療と並行して、生活習慣の改善も重要です。禁煙や栄養バランスの取れた食事、十分な水分摂取を心がけましょう。
歯周病の治療法

口臭の原因となる歯周病を治療するために、歯科医院で行われることについて説明します。
歯周基本治療
歯周基本治療は、歯周病の進行度にかかわらず、最初に行われる治療です。歯や歯根の表面に付着したプラークや歯石を取り除くスケーリング、ざらつきや汚染された組織を除去して歯根の表面をなめらかにするルートプレー二ングなどが行われます。
歯石は、除去されずに時間が経ったプラークが唾液の成分などと結合したもので、強固に歯に付着しているため、歯ブラシでは除去できません。歯石の表面はザラザラしており、さらにプラークが付着しやすい状態になるため、歯科医院で除去する必要があります。
スケーリングやルートプレー二ングでプラークや歯石を除去することで、細菌の温床を取り除くことができます。
また、毎日の歯磨きで患者さま自身がプラークを除去できるようになることが大切です。そのため、ブラッシング指導を行い、適切な歯磨き方法の指導が行われます。
歯周外科治療
歯周基本治療で症状が改善されない場合や、歯周病が進行している場合には、歯周外科治療が行われます。歯茎を切開して歯周ポケットの奥深くのプラークや歯石を除去するフラップ手術や、特殊な材料を用いて部分的に失われた骨を再生させる再生療法などが行われます。
メインテナンス
歯周病治療後は、定期的なメインテナンスが重要です。歯科医院で定期検診を受けることで、歯周病の再発を防ぎ、問題が生じていた場合にも早期に対応できます。
まとめ

歯周病による口臭は、細菌の繁殖や炎症が主な原因です。セルフチェックや専門的な治療を活用し、口臭対策を徹底しましょう。口臭が気になる方は、歯科医院で適切な診断と治療を受けてください。
品川港南歯科・矯正歯科クリニックでは、痛みや施術時間を抑えながら自然な仕上がりの治療を目指しています。マウスピース矯正やセラミック治療、虫歯治療、ホワイトニングなどにも力を入れています。